構成/「週刊電業特報」編集部 電気設備工事業界のギョーカイ紙です
暮らしに欠かすことのできない存在だからこそ、電気と電気工事(DEN-KOU)のことを、すこしマジメに、そしてオモシロおかしく発信していきたい。
電気と電気工事(DEN-KOU)のいろいろな側面を知っていただきたいというわけで、こんなブログをはじめることにしました。
*
ちなみに当サイトでいうエレクトリシャンとは古今東西、電気の工事や保守にたずさわってきた電気工事士(当サイトではDEN-KOUさんとも表現します)や建設現場の電気の施工管理をする人たち、電気の森羅万象を探求する研究者に至るまで、およそ電気にかかわる仕事を実践している(してきた)すべての人たちへの敬称であり総称です。
Eテレの楽しい元気番組《昆虫すごいぜ!》にリスペクトをこめつつこういわせていただきたい《エレクトリシャンすごいぜ!》《DEN-KOU すごいぜ!》
【プロローグSEAN 1】

夜空をきれいに彩るイルミネーション
イベントとして日常化したのは1990年代以降といえます。
でも日本に初めてイルミネーションが登場したのは、1903(明治36)年とかなり古い。あの大久保利通が欧米の万博の向こうを張って!? 創設した『内国勧業博覧会』(第1回目は上野)の第5回目に当たる『大阪・内国勧業博覧会』の会場でのことでした。
現代のイルミネーションは、LED30万球・40万球などが当たり前になっていますが、『第5回内国勧業博覧会』に初登場したイルミにはいくつの電灯が使われたと思いますか?
【プロローグSEAN 2】

1957(昭和32)年6月の誕生から今年で63年目を迎えた東京タワー、本名は「日本電波塔」さんです。
2010(平成22)年3月に建設途上の東京スカイツリー(最終的には634m)に抜かれるまで、東京タワー(333m)は日本一の高さを誇る建造物でした。
怪獣映画などで、怪獣たちに何度壊されようとそのたびに雄々しくよみがえり(!?)日本のシンボルであり続けた我らが東京タワー、その建設や保守の一翼を担ったのは、数多くのエレクトリシャンたちでありDEN-KOUさんたちです。
ところで東京タワーができるまで、日本一の高さを誇った 312mの電波塔があったのをご存じですか?
【プロローグSEAN 3】

現代建築の技術の粋をかたむけ完成した新国立競技場。
今年開催の2020東京オリパラのシンボル施設でもあります。
この新国立競技場の敷地にかつてあった、1964東京オリンピック(パラリンピックは別会場)のシンボル施設だった旧国立競技場と同様、数多くのエレクトリシャンたちDEN-KOUさんたちが、建設の一翼を担いました。
そして新国立競技場のテーマは、先端技術と自然環境とのコラボ。
その意気やよしとばかりに、近隣の代々木公園や明治神宮に暮らす野鳥たちの一部が早くも新国立競技場への「お引っ越し」準備中だそうです。
【プロローグSEAN 4】

遊園地の主役は、いわずと知れた電気仕掛けのアトラクション。
大観覧車・メリーゴーランド・ジェットコースターから、かわいいオモチャの楽隊に至るまでが電気で動きます。
さらに夜ともなれば、めくるめくネオンサインの輝きのなかで、電気仕掛けのアトラクションたちは、私たちをさらに深いファンタジーの世界へと誘ってくれます。
エレクトリシャン! DEN-KOUさん! グッジョブ!
【プロローグSEAN 5】

野菜が電気の光で育つ街なかの野菜工場。
電灯の光で、季節を問わずつくられ出荷される花々(電照菊など)もあります。
LEDの進化で、野菜も花もこれからは街なか生まれが当たり前になる?
事の是非はともかく、シャッター通りの再活用にも効果が見込まれる電気仕掛けの街なか野菜工場には、夜ともなれば新鮮な野菜を仕入れにくる料理人の姿も 時折りみられるようです。
【プロローグSEAN 6】

都心部に次々と誕生するスマートシティは、いわば電気仕掛けの新街区。
この新街区ができるまでのプロセスだけでなく、50年60年と続く維持・保守活動を支えていくのも、エレクトリシャンたち DEN-KOUさんたちです。
電化がさらに進むこれからの時代、電気の維持・保守(保安活動)はますます重要になっていきます。
でも、その壁になりそうなのがエレクトリシャン全般とくにDEN-KOUさんの志望者不足の傾向です。
次代を担う若者たちへの「電気のお仕事」の重要性、素晴らしさの発信は、電気設備工事業界にとって、目下最大のミッションの一つです。
【プロローグSEAN 7】

日本の経済成長のバロメーターの一つは、盛り場におけるネオン・サインの輝きの大きさでした。
100万ドルの夜景1000万ドルの夜景、電気の無駄遣いにもみえますが、おお、なんという華やかさだったことか。
現代の夜景の主役は、LEDを使ったイルミネーション。
そのぶん、大都会の夜景もだいぶ落ち着いてみえます。
そんな現代のイルミ中心の夜景もいいけど、かつてのド派手なネオン・サインの輝きも懐かしさを催させます。
そしてもちろん、それらの光の饗宴を支えてきたのも、エレクトリシャンたちでありDEN-KOUさんたちです。
【プロローグSEAN 8】

日本で最初に走った鉄道は、いうまでもなく1872(明治5)年新橋~横浜間を、汽笛一声走り抜けたSL。
では、日本で最初に走った電車は?
それは1895(明治28)年にできた京都電気鉄道でした。
走行区間は「下京区東洞院通東塩小路踏切~伏見町字油掛」、総延長距離は6.4㎞だったといいます。
この京都電気鉄道に電力を供給したのは、1891(明治24)年完成の蹴上発電所、すなわち琵琶湖から京都市内に今も水を導いている、あの琵琶湖疎水を活用した日本初の営業用水力発電所です。
当時は、現在のような広大なエリアに電力供給できる大型の発電所は存在しませんでした。
京都電気鉄道向けに建設された蹴上発電所と同様、東京や大阪にも小さな発電所がそれも街なかに建設されるのが常でした。
送電用の鉄塔や電信柱が構築されていくのは、もっともっと後の時代のことになります。
【プロローグSEAN 9】

日本の戦後の経済成長を支えたのは、全国各地に建設された湾岸の工業地帯です。
その代償は、四日市をはじめとする各地の公害現象でした。
空気を汚す公害の代名詞のようになってしまった四日市ですが、実は現在四日市がその後に開発した公害防止の技術が世界中から注目を集めています。
とくに工業開発が現在進行形で進むアジア諸国アフリカ諸国などにとって、四日市の工業開発と公害との闘いの軌跡は、教科書のような存在なのです。
そんな話題も当サイトではリポートしていきたいと思います。
【プロローグSEAN 10】

日本最初の地下鉄・銀座線は、今年で開通から93年目。
浅草と並ぶもう一方の発着駅銀座線・渋谷駅は、1938(昭和13)年に誕生しましたが、2020年1月、82年目にして場所を移動しました。
ところで、地下鉄・銀座線の前にもう一つの銀座線が走っていたのをご存じですか?
それは都電・銀座線(通称・正式には都電1系統)です。
都電・銀座線の営業区間は品川駅~上野駅前まででしたが、1964東京オリンピック前後から深刻化した交通渋滞緩和のため、都電は次々廃止され、都電・銀座線も1967(昭和42)年に廃止されます。
また都電・銀座線は、出発点(明治時代の私鉄時代)において、電力供給源として自前の発電所(品川)を持っていました。
そんな話題も含め、都電・銀座線と地下鉄銀座線の関係など、面白いエピソードがたっぷりあります。
当サイトでは、そんな話題も準備中です。
【プロローグSEAN 11】
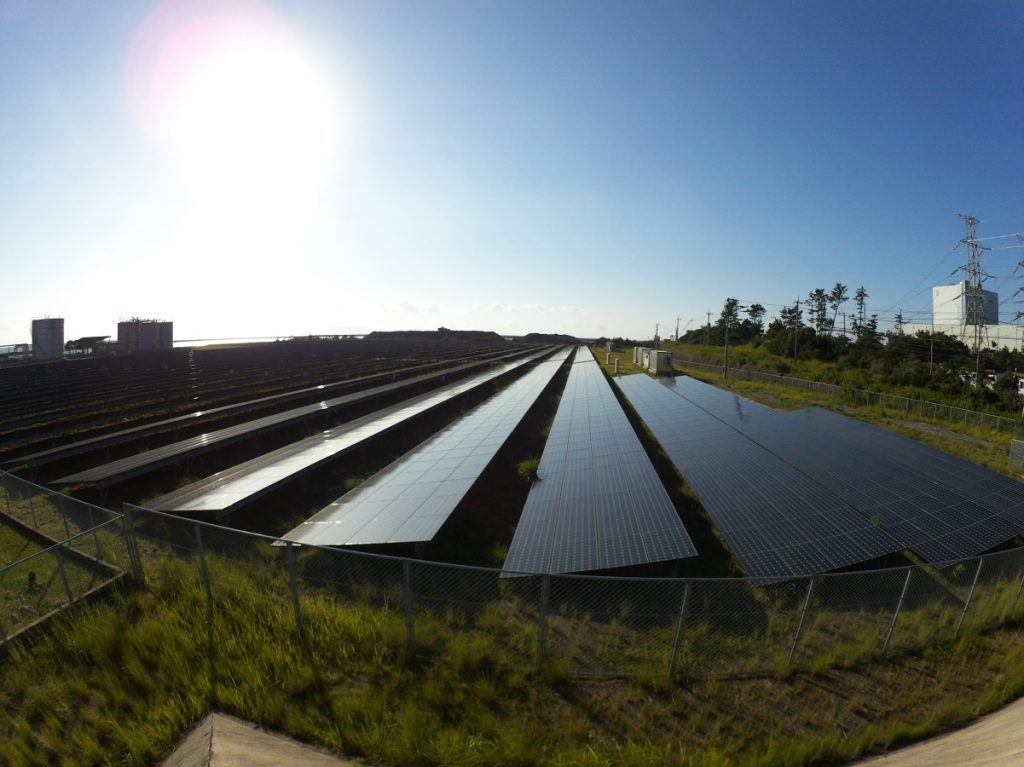
人類の電化生活がはじまって約150年超。
その間に登場した電力源は、水力・火力・原子力が代表的です。
近年は持続可能なエネルギーとしての、自然エネルギーが注目され続けていますが、安全かつ安定的に電力を生み出すことができ、資源としても無限に近い埋蔵量をもつモノを、人類はいまだに手にすることができないでいます。
電力事業の保安要員(担い手)不足も深刻ですが、究極のエネルギー供給源の探求はこれからの人類の最大の課題の一つといえます。
研究部門を担うエレクトリシャンたちの頑張りにぜひとも期待していきたいですね!
【プロローグSEAN 12】

当サイトでは「旅」がらみの話題も随時発信していきます。
たとえば、写真の「ねぷた」は青森県五所川原市で明治40年頃に誕生した、「立佞武多・たちねぷた」です。
「立佞武多・たちねぷた」の特徴は、その名の通りタテに長いこと、高さが20mあるものも珍しくありません。
この「立佞武多・たちねぷた」現在では、青森市のねぶた・弘前市のねぷたと並ぶ東北の真夏の風物詩ですが、大正時代にいったん衰退します。
タテに長くなり過ぎたため、電化とともに登場した電線に引っかかるようになってしまったのです。
立佞武多はしかし1998年に復活します。
細かい話は省きますが、中心市街地の電線地中化が進み、タテに長くてもOKになったことも復活の大きな要因でした。
同時に青森・弘前も含め、ねぷた・ねぶたはLED新時代を迎えています。
そんな話題も「乞うご期待!」です。
(取材・写真・文/未知草ニハチロー)

